ホーム
「野辺地」という地名がはじめて文献に見えるのは、南北朝時代の建武2年(1335)ですが、町内には寺ノ沢遺跡(縄文前期)、槻ノ木遺跡(縄文中期)、枇杷野遺跡(縄文後期)、陣場川原遺跡(縄文後期)などの遺跡が分布しており、これらのことから、すでに先史時代から人々がこの地に住んでいたことが知られています。
立地的に古くから交通の要衝として発展してきましたが、特に延宝年間(1673~1680)から明治の初年にかけて、豪商と呼ばれた地元の野村治三郎や野坂勘左衛門、さらには北陸の銭屋五兵衛などの千石船が往来し、日本海沿岸諸港並びに大阪、函館などと盛んに交易し、南部藩有数の商港として繁栄しました。
明治22年4月1日の市町村制施行によって野辺地村、馬門村、有戸村が合併して野辺地村となり、同30年8月28日には町制を施行し、平成19年に町制施行110周年を迎え、現在に至っています。
町 章

野辺地の頭文字である「の」の字を表徴するとともに、躍
進を連想させる波頭をあわせ図形化したもので、躍進、発
展、団結を表現したものです。
(昭和36年11月24日制定)
町の花「はまなす」
 海辺に咲く花「はまなす」は、丈は短いが、強い浜風に耐
海辺に咲く花「はまなす」は、丈は短いが、強い浜風に耐
える様は、横に手を伸ばし、輪(和)を広げているようで
す。
歌人石川啄木が「潮かおる北の浜辺の砂山のかの浜なすよ
今年も咲けるや」と詠んだように、北のまち野辺地のイメ
ージにあいます。
町の鳥「かもめ」
 日本最古の灯台といわれる常夜燈を眼下に、水面を悠然と
日本最古の灯台といわれる常夜燈を眼下に、水面を悠然と
飛ぶ「かもめ」は、南部藩の商港として栄えた野辺地町に
ふさわしい鳥です。
「のへじ夏だよ 潮路のかもめ」と野辺地音頭にも歌わ
れ、親しまれており、夏祭りの海上渡御に飛び交う「かも
め」は町のみなぎる活力を感じさせます。
町の木「さくら」
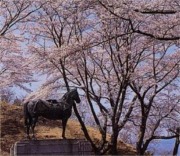 町民憩いの場である愛宕公園の「さくら」は、私たちをい
町民憩いの場である愛宕公園の「さくら」は、私たちをい
つも心優しく見守ってくれています。
当町が分布の北限にあたる公園内の「エドヒガシ」、西光
寺の「シダレザクラ」は、いずれも町指定天然記念物とな
っており、樹齢250年をかぞえ、毎年みごとな花をつ
け、町のシンボルとなっています。
立地的に古くから交通の要衝として発展してきましたが、特に延宝年間(1673~1680)から明治の初年にかけて、豪商と呼ばれた地元の野村治三郎や野坂勘左衛門、さらには北陸の銭屋五兵衛などの千石船が往来し、日本海沿岸諸港並びに大阪、函館などと盛んに交易し、南部藩有数の商港として繁栄しました。
明治22年4月1日の市町村制施行によって野辺地村、馬門村、有戸村が合併して野辺地村となり、同30年8月28日には町制を施行し、平成19年に町制施行110周年を迎え、現在に至っています。
町 章

野辺地の頭文字である「の」の字を表徴するとともに、躍
進を連想させる波頭をあわせ図形化したもので、躍進、発
展、団結を表現したものです。
(昭和36年11月24日制定)
町の花「はまなす」
 海辺に咲く花「はまなす」は、丈は短いが、強い浜風に耐
海辺に咲く花「はまなす」は、丈は短いが、強い浜風に耐える様は、横に手を伸ばし、輪(和)を広げているようで
す。
歌人石川啄木が「潮かおる北の浜辺の砂山のかの浜なすよ
今年も咲けるや」と詠んだように、北のまち野辺地のイメ
ージにあいます。
町の鳥「かもめ」
 日本最古の灯台といわれる常夜燈を眼下に、水面を悠然と
日本最古の灯台といわれる常夜燈を眼下に、水面を悠然と飛ぶ「かもめ」は、南部藩の商港として栄えた野辺地町に
ふさわしい鳥です。
「のへじ夏だよ 潮路のかもめ」と野辺地音頭にも歌わ
れ、親しまれており、夏祭りの海上渡御に飛び交う「かも
め」は町のみなぎる活力を感じさせます。
町の木「さくら」
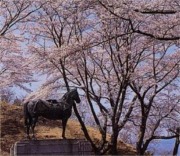 町民憩いの場である愛宕公園の「さくら」は、私たちをい
町民憩いの場である愛宕公園の「さくら」は、私たちをいつも心優しく見守ってくれています。
当町が分布の北限にあたる公園内の「エドヒガシ」、西光
寺の「シダレザクラ」は、いずれも町指定天然記念物とな
っており、樹齢250年をかぞえ、毎年みごとな花をつ
け、町のシンボルとなっています。
最新情報
| 2025/01/24 | 河原決明(かわらけつめい)をご存じですか?野辺地町観光物産PRセンター |
|---|
| 2023/07/12 | のへじ祇園まつり 開催期間 2023/08/17~2023/08/20 |
|---|
| 2022/04/12 | 野辺地特産のホタテを堪能してみませんか? |
|---|
| 2021/10/12 | 旧野村家住宅離れ(行在所)夜間特別公開をします! 開催期間 2021/11/03~2021/11/03 |
|---|
| 2021/01/18 | 河原決明をご存じですか?野辺地観光物産PRセンター |
|---|